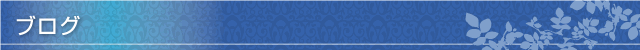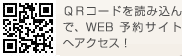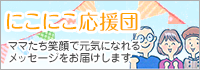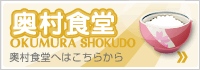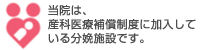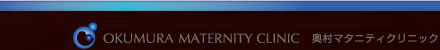当院の耳より情報をお届けします。
奥村院長のつぶやきも必見!
第2回生殖補助医療胚培養士セミナーに参加して
 先日、10月末に日本哺 乳動物卵子学会が主催する「第2回生殖補助医療胚培養士セミナー」に参加してきました。
先日、10月末に日本哺 乳動物卵子学会が主催する「第2回生殖補助医療胚培養士セミナー」に参加してきました。
日本哺乳動物卵子学会とは、“生殖補助医療胚培養士”という資格の認定・審査を行っている学会なのです!
今回pick upして紹介したい演題は、山形大学大学院農学研究科の木村直子先生による「卵子における酸化ストレスと発生障害」です。
酸化ストレス…、あまり馴染みのない言葉ですが、なんとなく卵子に悪影響を及ぼしそうな感じはしますよね。
大気中のO2濃度は約20%、CO2濃度は約0.04%ですが、卵を培養するインキュベーター内のO2、CO2濃度はともに約5%と、O2濃度がかなり低く、私たちとは住む環境が全く違うのです!
卵にとっては体内と同じ、この濃度が一番快適なのです。
そのため、インキュベーターの外は、高濃度O2にさらされるため、卵はストレスを受けるのです。
酸化ストレスを受けると、細胞毒性の高い“活性酸素”という物質が増加します。
細胞内では、発生した活性酸素を除去し、酸化状態から還元状態に戻す種々の抗酸化物質が産生され、恒常性(レドックスバランス)を維持する機能を持っています。
培養卵は体内発生卵に比べてより多くの酸化ストレスを受けるため、活性酸素量が高くなります。卵内で発生した過剰な活性酸素を除去しきれなくなると、レドックスバランスが崩れ、DNA変性や脂質の酸化、タンパク質の酸化などにより細胞内小器官の損傷や機能障害が起こって、それらが修復されない場合、最終的には機能不全により卵は死に至ってしまうのです!
しかし、観察や培地交換が必要なため、ずっとインキュベーターの中…というわけにはいかないので、できるだけ卵にストレスを与えないように、インキュベーターから外に出す時間を極力短くし、培養液の上にオイルをはって、O2、CO2濃度変化が少なくなるように努力しています。
研究段階ではありますが、酸化ストレスを軽減できるような培養液の開発も進んでいるそうです。
また、卵の老化の原因は活性酸素にあるといわれており、酸化ストレスの克服は卵のアンチエイジングにも繋がり、IVFに革命をもたらしてくれそうです!
日本IVF学会を聴講して
9月18・19日と日本IVF学会を聴講してまいりました。
この学会は私がこの施設に勤めだしてから(当時は奥村医院でした(*^_^*))欠かさず参加している学会で、いつもはひとりぼっちかもしくは先生と2人……で発表を聞かせていただいていたのですが、今年はなんと!培養室のメンバー3人で、先生も含めて4人で参加することができました(勤務の都合上、全員がずっと…というわけにはいかなかったのですが)。
今回のテーマは『温故知新』 皆様ご存じのとおり「故(ふる)きをたずねて新しきを知る」ということですが、講演の中で「故きを馬鹿にしていては新しきに馬鹿にされる!」というお言葉にハッとさせられました。基礎があってこその現在。次々に新しいことばかりを追いかけていくのではなく、時には立ち止まって足元を固めることが必要なのだと背筋を伸ばしてしっかりと聞いてきました。
最近は完全自然周期で採卵を行うことに力を入れていらっしゃる施設があります。全く初期の体外受精は自然周期だったのですからまさしく『温故知新』なのだということです……とこの報告記を書いているときにイギリスのエドワーズ教授がノーベル賞を受賞されたとのニュースが!!エドワーズ教授は世界で初めて体外受精を成功させた方で、そのおかげで現在の高度生殖医療の発展があるのです。あまりのタイムリーさに鳥肌が立ってしまいました。私たちは今まさに高度生殖医療に関わっているのだ!と胸を張って言えるように頑張らなくてはなりませんね。<(`^´)>
それと高度生殖医療の施設についても話題になっていました。現在は全国に5~600の施設がありここ数年はほぼ横ばい状態といわれていますが所在には偏りがあり、佐賀県には一つの施設もないそうです。そしてここ和歌山県も……施設数の少ない県に挙がっていました。一人でも多くの患者様に『近くにあってよかったわ。』と言っていただけるようにスタッフ一同努力してまいります。
日本受精着床学会の学術講演会に参加して
報告が遅くなりましたが、平成22年7月28日・29日にパシフィコ横浜で開催された日本受精着床学会の学術講演会に参加してきました。
周産期医療から見た不妊治療
 平成22年6月5日に大阪南部不妊懇話会という勉強会に参加してきました。
平成22年6月5日に大阪南部不妊懇話会という勉強会に参加してきました。
「周産期医療から見た不妊治療」という演題で 川崎医科大学の産婦人科学教室教授 下屋 浩一郎先生のご講演でした。
周産期医療って…?
妊娠22週から生後7日目までの赤ちゃんとお母さんのための医療のことで、要するにお産にまつわる医療のことなのです。
講演は、基礎疾患を持っている患者様やハイリスク妊娠・分娩が予想される患者様は不妊治療を始める前にきちんと理解し、治療をできる病気に関しては治療しましょう、という内容でした(カンタンにしすぎました…下屋先生、すみません)。
高齢の不妊患者様は時間との戦い、自分の体のことは二の次でとにかく妊娠……と考える方もいらっしゃるでしょうが、高血圧や糖尿病があったりするとせっかく妊娠しても継続が難しかったりとても危険なお産になったりするのです。患者さんの中には妊娠がゴールと考えているように感じる方もいらっしゃいますが、妊娠も出産もあくまで通過点。その先には家族で過ごす長い期間があるのですから元気にお産を迎えていただきたいと思います。
また先生は『ARTによる妊娠をハイリスクにしているのは多胎妊娠です。』と強くおっしゃっていました。そういえば『一度にすむから双子が欲しい』と軽くおっしゃる患者様がときどきいらっしゃいます((+_+))。双子のお産ってリスクが高いんですよね……。私たちは患者様のためにもハイリスク妊娠を避けなければいけません。そこのところは理解していただきたいと思います。
最後になりましたが培養室に頼もしいスタッフが増えました。さらに充実した培養室になるように3人力を合わせて頑張りますのでどうぞよろしくお願いします。
はじめまして、培養士よりご報告。
平成22年1月9・10日、日本臨床エンブリオロジスト学会に参加してきました。
エンブリオロジストってご存知でしょうか?
エンブリオロジストとはエンプリオ(胚=卵ちゃん)を扱う技術者のことなのです。
どちらかと言うと培養室の中にこもっていることが多いのですが、培養室では皆さまの大切な胚をお預かりしています。
エンブリオロジスト学会とは、エンブリオロジストが主体となって知識と技術の向上をめざしたエンブリオロジストのための学会なのです。
各施設からたくさんのエンブリオロジストが、今回の東京・墨田区の会場に集まりました。
技術の進歩に遅れないよう、新しい情報を得ようと皆さん大変熱心です。ここで得られた情報をキチンと患者さまに還元できるように、努力しなくては・・・と澄んだ寒い空気の中、改めて身の引き締まる思いのした2日間でした。
ところで、墨田区と言えば2011年開業を目指して東京スカイツリーが建設中だそうです。そこで写真を1枚。
会場近くの建設でしたが、東京の街並みは日々変化しているようです。